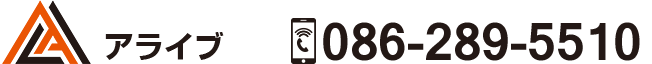こんにちは!岡山の解体専門業者、株式会社アライブです。
火災によって建物が被害を受けた場合、解体費用や手続きについてお悩みの方が多いのではないでしょうか?
この記事では、火災後の解体費用の相場や費用を抑えるポイント、必要な手続き、放置するリスクなどを 図や表を交えて 分かりやすく解説します。
✅ この記事を読むと分かること
火災で被害を受けた建物の解体を検討されている方は、ぜひ最後までお読みください!
火事後の解体費用の相場はいくら?

火災後の解体費用は 通常の解体費用よりも高くなる 傾向があります。その理由は、以下の通りです。
🔥 火事後の解体費用が高くなる理由
✅ 燃えた建材はリサイクルできず、廃棄物処理費用が増加
✅ 建物が脆くなっているため、安全対策に手間がかかる
✅ 燃え残りの有害物質(アスベスト等)の処理が必要になるケースも
📊 坪単価あたりの解体費用目安
| 建物の構造 | 通常の解体費用 (坪単価) | 火災後の解体費用 (坪単価) |
| 木造住宅 | 3万円~5万円 | 4万円~6万円 |
| 鉄骨造住宅 | 4万円~6万円 | 5万円~7万円 |
| RC造(鉄筋コンクリート) | 6万円~8万円 | 7万円~9万円 |
💡 ポイント
火災後の解体費用は 通常の1.2~1.5倍 になることが多い
👀 こんなケースは費用が高くなる!
✅ アスベスト を含む建材が使われている場合
✅ 建物が密集した住宅地 で、重機が使えない場合
✅ 撤去する瓦礫の量が多い 場合
火災後の解体費用を抑えるためのポイントと支援制度
解体費用を抑えるためには、いくつかの方法があります。
✅ 複数の業者に見積りを取る
1社だけで決めず 3社以上 から見積りを取りましょう。業者によって 価格やサービス内容に違い があります。
📌 ポイント
- 見積もりは無料の業者を選ぶ
- 「火災解体の実績」がある業者を選ぶ
✅ 自分で片づける
残せるものは撤去し、瓦礫の量を減らす ことで、処分費用を節約できます。
⚠️ 注意点
- 焼けた建材には有害物質が含まれることがあるため、防護服やマスクを着用
- 大量の瓦礫を処分する場合、市町村の指示に従う
✅ 火災保険を使う
火災保険に加入している場合、解体費用が補償される可能性 があります!
📌 保険適用の流れ
1️⃣ 被害状況の写真を撮影
2️⃣ 罹災証明書を取得
3️⃣ 保険会社へ連絡し、適用条件を確認
💰 利用できる補助金制度
| 制度名 | 支援内容 |
| 災害見舞金制度 | 生活再建のために支給される自治体の支援金 |
| 被災者生活再建支援制度 | 解体・修繕のための費用を一部補助 |
| 一般廃棄物の処理手数料の減免 | 火災ごみの処理費用を一部または全額免除 |
火事後に行うべき7つの対応とその手順
火災後の建物を解体するまでに、次のような手続きが必要です。
📷 ① 被害状況の写真を撮る
火災保険や補助金申請のために 証拠写真を残すことが重要 です。
📌 撮影ポイント
✅ 建物の外観・内観
✅ 焼けた家財や壁の損傷状況
✅ 燃え残った部分と被害が大きい部分
📝 ② 罹災証明書の発行
市役所や役場で 罹災証明書 を発行してもらいましょう。
📌 メリット
✅ 火災保険の請求に必要
✅ 解体費用の補助金申請に必要
📞 ③ 保険会社への連絡
加入している火災保険の補償内容を確認し、必要書類を準備します。
🔑 ④ 貴重品の回収を行う
火事の被害を受けた建物から、再利用できる家財や貴重品を回収 します。
🏡 ⑤ 近所へご挨拶
解体工事前には 近隣住民に挨拶をしておくとトラブルを防げます。
🏗️ ⑥ 解体工事会社へ依頼
経験豊富な解体業者を選ぶことが重要 です!
📌 業者選びのポイント
✅ 「火事解体」の実績がある
✅ 見積りが明確で追加費用がない
🚰 ⑦ ライフラインの停止や仮住まいの手配
水道・電気・ガスの停止手続きを行い、仮住まいを確保しましょう。
火事にあった建物を放置する危険性やリスク

火事で焼けた建物を放置すると、以下のような リスク があります。
- 瓦礫や燃えがらの飛散 → 近隣住民とのトラブルに発展
- 倒壊の危険性 → 建物がもろくなり、強風や地震で崩壊
- 悪臭や害虫の発生 → ゴミや廃材が原因で衛生問題に
- 火事解体費用の増加 → 放置するほど解体費が高くなる
- 特定空き家に指定される → 行政指導や固定資産税の増額
🔥 火災後の解体工事の具体的な流れ
火災後の解体工事には いくつかのステップ があります。
スムーズに進めるために、 「何を・いつ・どのように」 進めるのかを理解しておきましょう。
📌 火災後の解体工事の流れ(全体像)

以下の6つのステップ で進めていきます。
📝 ① 現地調査・見積もり依頼
📄 ② 罹災証明書の取得 & 各種手続き
🤝 ③ 解体業者と契約
🚜 ④ 解体工事の着手
🔍 ⑤ 産業廃棄物の処理 & 更地化
✅ ⑥ 竣工・完了報告
以下に 詳しい工程とポイント を解説します!
📝 ① 現地調査・見積もり依頼
火災後の建物は通常の建物よりも解体が難しい ため、業者に 現地調査を依頼 して見積もりを出してもらいましょう。
| ✅ チェックポイント | 🔍 確認すること |
| 建物の構造 | 木造・鉄骨造・RC造 |
| 損傷の度合い | 燃え残り・倒壊の危険性 |
| アスベストの有無 | 事前検査が必要な場合あり |
| 近隣環境 | 重機が入るスペースの有無 |
| 瓦礫の量 | 処分費用がどのくらいかかるか |
💡 ポイント
✅ 3社以上の業者に見積もりを取る
✅ 火災解体の実績がある業者を選ぶ
📄 ② 罹災証明書の取得 & 各種手続き
火災後の解体工事には 「罹災証明書」 が必要です。
📌 罹災証明書とは?
市役所が発行する 「火災の被害状況を証明する書類」 で、補助金や減税の申請に必要になります。
🏛️ 罹災証明書の申請手順
1️⃣ 市役所へ申請(申請書を提出)
2️⃣ 職員による現地調査(家屋の被害状況を確認)
3️⃣ 罹災証明書の発行(1週間~10日ほどかかる)
💡 あわせて手続きすべきこと
✅ 火災保険の申請(証明書が必要)
✅ 自治体の補助金申請(被災者支援制度を活用)
🤝 ③ 解体業者と契約
見積もり・手続きが完了したら、解体業者と契約を交わします。
📌 契約時の確認ポイント
✅ 追加費用の発生条件(見積もりの範囲を超える場合)
✅ 工事の期間・工程(何日かかるか?)
✅ 近隣対策(騒音・振動の説明)
💡 火災後の解体では、通常よりも時間がかかることがあるので要注意!
🚜 ④ 解体工事の着手
いよいよ解体工事が始まります!
火災後の建物は もろくなっているため、安全対策が重要 です。
📌 解体工事の工程
① 重機を入れるための準備 🏗️
➡️ 周囲の建物を傷つけないように養生シートを設置
② 瓦礫の撤去 🧹
➡️ 手作業で細かい瓦礫を片付ける
④ 地中の確認 🔍
➡️ 地下埋設物(古い基礎など)がある場合は撤去
📷 解体工事のビフォー・アフター
解体前
🏚️【燃えた家屋の写真】
解体後
🏞️【更地になった土地の写真】
💡 ポイント
✅ 周囲への粉じん・騒音対策 をしっかり行う
✅ 火事で焼けた廃材は特別処理 が必要
🔍 ⑤ 産業廃棄物の処理 & 更地化
解体後は大量の廃棄物が発生するため、適切な処理が必要 です。
📌 主な廃棄物の種類
| 🔥 火災解体で発生する廃棄物 | 📌 処理方法 |
| 焼けた木材 | 産業廃棄物として処理 |
| 瓦・コンクリート破片 | リサイクル or 産廃処理 |
| 燃え残った家財 | 特別廃棄物処理が必要な場合も |
💡 ポイント
✅ 自治体の処理費用減免制度 を活用できる場合がある
✅ 信頼できる業者に処分を依頼(不法投棄を防ぐ)
✅ ⑥ 竣工・完了報告
工事が終わったら、業者から完了報告を受けます。
土地を売却する場合や、再建築する場合は 「滅失登記」 も忘れずに行いましょう!
📌 滅失登記とは?
➡️ 解体した建物が「存在しない」ことを法務局に届け出る手続き。
✅ 登記しないと固定資産税がかかり続ける ので要注意!
🎯 火災後の解体工事の流れまとめ
現地調査・見積もり
↓
罹災証明書の取得 & 手続き
↓
解体業者と契約
↓
解体工事開始
↓
産業廃棄物の処理
↓
完了 & 滅失登記
🔚 まとめ
🔥 火災後の解体工事は、通常の解体よりも手続きが多く、費用が高くなる傾向があります。
しかし、 補助金や保険を活用すれば費用を抑えられる ため、事前準備をしっかり行いましょう!
株式会社アライブでは、岡山地域密着をモットーに空き家、建て替え時の解体作業をおこなっております。
是非!解体の事なら株式会社アライブにお任せください! 🚜✨